昨日、以下のプログラムにおいて、第41回の「ナノプラネットゼミ」が開催されましたので、その概要を続報します。
プログラム
10:00~10:30 話題提供① 「タイム(ハーブ)の効用について」 大成京子
10:30~11:00 話題提供② 「16時間ダイエットの実践」 大成由音
10:00~10:30 話題提供① 「タイム(ハーブ)の効用について」 大成京子
10:30~11:00 話題提供② 「16時間ダイエットの実践」 大成由音
11:00~11:40 話題提供➂ 「最近のトピックスと大成研究所の課題」 大成博文
11:40~12:00 総合討論
以下、昨日の記事の続きです。
2)「脂肪の燃焼、ダイエット、生活習慣予防」
胃の中で脂肪が溶けて完全に消化されるには約10時間が必要であり、その脂肪の燃焼を行なうのに16時間ダイエットが有効なのだそうです。
これによって、糖尿病や心疾患の素となる内臓脂肪を分解することが注目されています。
単なるダイエットではなく、一日二食を無理なく遂行することによって生活習慣病の予防も可能になるのです。
私どもの場合、夕方の5時から6時にかけて夕食をとる場合が多く、その後は、何も食べません。
とくに、20時以降は、少量のヨーグルトをいただくだけにしています。
そして、翌朝は9時ごろに朝食をいただきますので、約15時間のダイエットをしていることになりますので、自然に生活習慣病予防にもなっていたことに気づきました。
おかげで、身体がスリムになってきて、お腹も膨らまないようになりました。
また、この歳になってきて、「腹八分目にして胃に負担をかけない」ことの重要性を認識し、それが普通にできるようになりました。
ほぼ青木先生の理論に近づいていたので、それも含めて討論を進めました。
3)「『オートファジー』のはたらき」
16時間ダイエットは、ある意味でお腹を「飢餓状態」にすることであり、その時には、お腹の動きが活発になり、グーグーと鳴り始めることを、私たちは知っています。
じつは、この時に「オートファジー」の働きが強められ、細胞が生まれ変わる機能が増し、感染症の予防や肌や筋肉の老化を防ぐことが明らかにされています。
この機能の研究によって、大隅良典博士がノーベル賞を2016年に受賞されています。
議論においては、このオートファジー機能について盛り上がりました。
また、この16時間ダイエットを実行中の話題提供者からは、いくつかの感想が示され、さらに議論が展開されました。
胃に負担をかけない、脂肪の燃焼、生活習慣病の改善、老化防止と若返り、いずれも直面している課題であり、大いに役立ちました。
③については、私が話題提供を行いました。
その時のスライドを示しておきましょう。
ひところの急激な円安傾向が、やや減少し、現在は1ドル136.7円です(8月23日)。
これから、再びより円安に向かうという予測も出始めました。
アメリカのリセッション(不景気)、インフレがより進行し、それぞれが、交互に押し寄せるという状況が、その円安、円高に微妙に影響しているようです。
また、FRBの金利上昇政策においては、年内に4%まで持って行くという予測も出てきています。
インフレーションは一度高騰に転じると止まらなくなるので、その情勢判断を厳密に行っているのではないでしょうか。
一方で、中国における不動産バブル経済の破綻が顕著になり、これにアメリカのバブル経済が弾けると、世界経済は暗澹たる状況に入っていくというという恐れも出ています。
世界同時バブル経済の破綻が明確になっていくのは、近いうちに起こると予測視されている株価の暴落だといわれています。
この経済的混乱は、政治の世界にも波及し、そのメルトダウンが進んでいます。
英国やイタリアの首相の辞任、スリランカの大統領の国外逃亡、バイデンの不人気の深まり、ネオコンの相次ぐ後退、そして日本のカルトの根深さなどが連動し、それがカサンドラクロスに向かっているのではないかという指摘がなされています。
これらは、新自由主義を土台にした権力構造の崩壊を示唆しており、同時に、その分権化が生まれてくることを意味しています。
このさまざまな分野における権力破綻をよく見据え、その分権化において何をなすべきかをしっかり考えていく必要があります。
その基本は、新技術の開発であり、それを梃(てこ)にしたブレイクスルーが重要です。
そのブレイクスルーに関する当面の課題として、次の3つが示されました。
1)この2~3年間の緑砦館における光マイクロバブル水耕栽培の成果についての総括がなされました。
アイコ、サンチュ、キュウリなどの野菜の特徴が明らかにされ、市販野菜との比較がなされました。
2)発芽促進および苗へ成長促進における特徴が示されました。
3)これらを踏まえ、新たな装置開発のアイデアが明らかにされました。
次に、K社から送付されてきたトマト栽培に関する根の成長を示した写真について議論しました。
すばらしい根の成長ぶりに感激するとともに、根の多さ、短期間における成長ぶりに驚嘆しました。
おそらく、非常によい環境下での光マイクロバブル水耕栽培の優位性が現れた事例ではないかとおもわれます。
3番目は、最近の七島イに関する取り組みの結果を課題を議論しました。
すでに、注目すべき結果が出現していますので、それらの商品化の検討を行うために、新たな研究開発補助金の申請を行うことを確認しました。
4番目は、この2年間の病院との共同研究の成果を踏まえ、それを、今後、どう展開していくのかに関する展望を示しました。
この課題は、非常に重要であり、いくつもの分野における新たな開発要素が生まれていますので、それらを、まずは基礎から、どう足場を固めるのか、さらには、それを足場にして、どう発展させるのかについて議論を行いました。
今回は、身近な問題から大成研究所の課題、世界経済の動向などに関する議論がなされ、非常に有益なゼミとなりました。
なお、次回の第42回ナノプラネットゼミの開催は、9月22日(木)10:00から開催予定です。
開催場所は、同じです。奮って、ご参集ください(この稿終わり)。

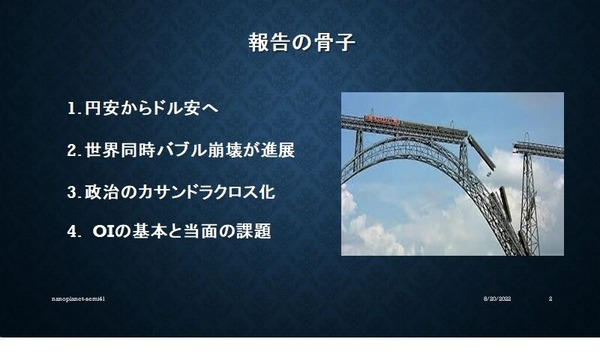

コメント